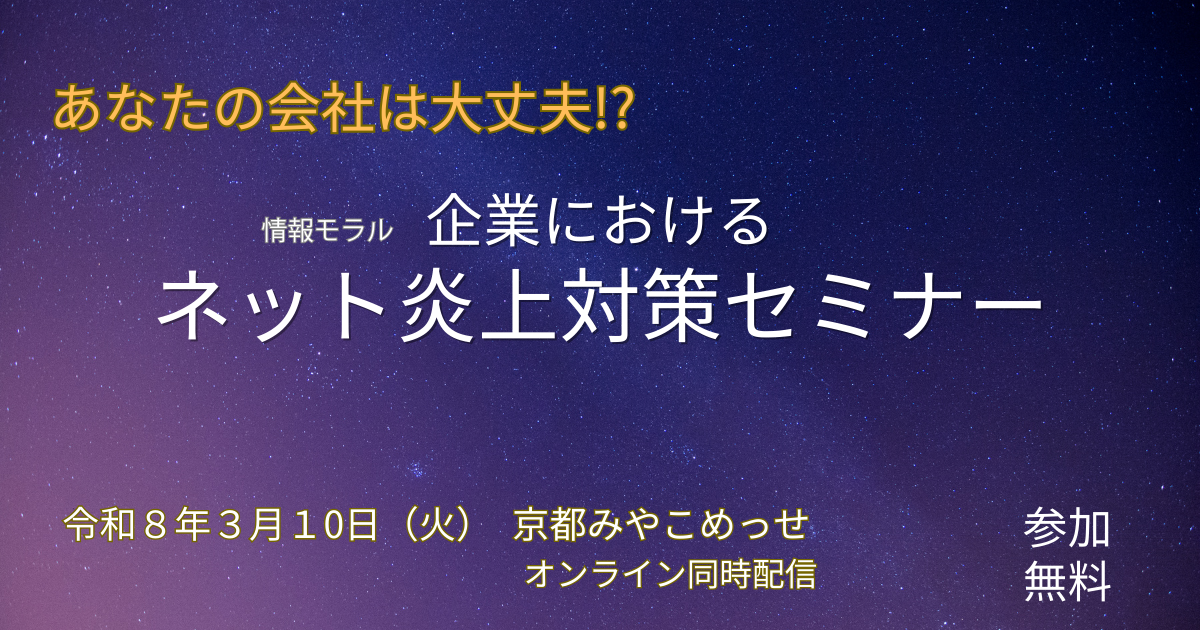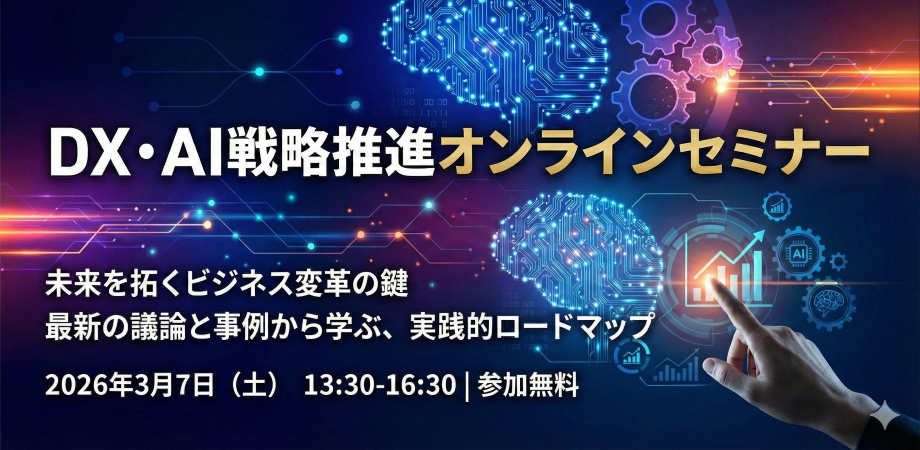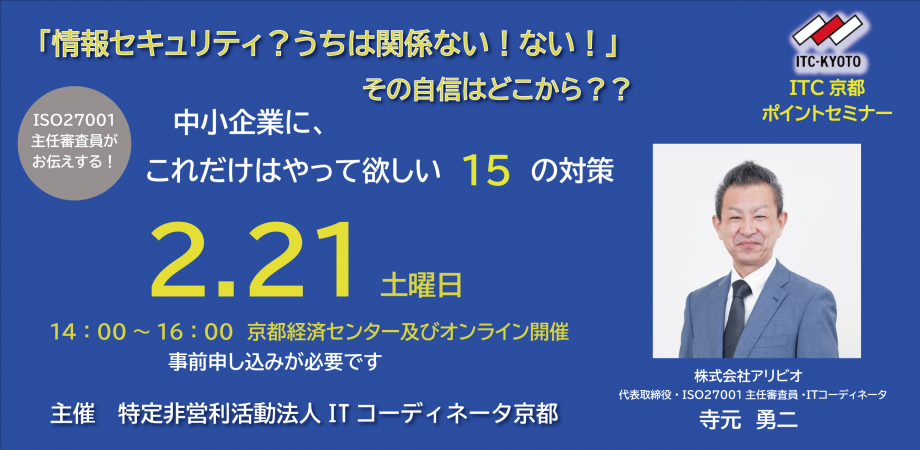〇市民生活に必要な情報をどう入手しますか?
私は豊橋市の会社に勤めていますが、週末は自宅がある京都で過ごしています。京都市内の知人を増やしたいと思い、ITコーディネータ京都にも加入させていただいています。もちろん、退職後は大好きな京都で過ごしたいと考えており、地元の企業やさまざまな組織のICT技術の活用の手助けができればと願っています。
さて、久しぶりの話ですが、妻が自治会の役員を引き受けることになりました。私も微力ですが、市民新聞などの広報媒体や回覧板を配達したり、会費や日本赤十字の寄付金などを集約したりといった仕事をこなしています。皆さんも同じような経験をされた人も多いでしょう。
私は、新聞や広報物を配達するたびに、いつまでこの仕事が続くのだろうと、疑問に思います。京都市でも公式LINEがありますし、ウェブサイトも充実してきました。どこかのタイミングで、誰が、自治会のあり方、市から住民への広報を抜本的に見直すのだろうと、モヤモヤすることが多いのです。
〇現状の課題
もう少し具体的な私の経験を述べてみます。昨年7月から豊橋市で単身赴任生活を送ることになりました。一人で引っ越して、一番最初に調べたのが、ゴミの捨て方です。どのように分別すればいいのか、生ごみはいつ出したらいいのだろう??幸いなことに、マンションの管理人さんからゴミ収集カレンダーを頂きました。そのカレンダーを冷蔵庫に貼って、日々確認をしています。
私もITコーディネータですので、住んでいるところを入力するとプッシュ配信で教えてくれる仕組みがあるといいのに!と思いました。私が真剣に調べなかったせいもあるのですが、日々、自分でカレンダーに入力して、ゴミを出していました。
ある日、市役所の知り合いと食事していて、ゴミの出し方をアプリで親切に教えてくれるといいのに!と言ったら、「ゴミ収集アプリがある!でも、あまり認知が進まないのだよね」という話になりました。どうやって広報したらいいのだろう?とお悩みの様子でした。
〇市民向けアプリの使い勝手を良くするには、どうすればいいのだろうか。
豊橋市役所は、他にもさまざまなアプリをリリースしています。防災アプリであったり、健康づくりアプリであったり。また、災害速報、イベント情報、市営施設の宣伝などSNSのアカウントも多いのです。少し古い情報になりますが、「豊橋市は市の公式交流サイト(SNS)アカウントが七十以上ある」という記事を読みました。https://www.chunichi.co.jp/article/661036 フェイスブック、ツイッター、Xなど、さまざまな媒体を活用しているとのこと。
しかし、市民、ユーザの立場になってみると、そんなにSNSのアカウントを登録し、閲覧するでしょうか?また、さまざまな行政のアプリをそれぞれインストールして、通知機能を活用し続けるでしょうか。
市役所の担当者が真面目にひたむきに仕事に取り組んでいることに敬意を払いつつ、もう少し市民の使い勝手を向上させる工夫をしたらよいのにと思います。
〇理想の市民アプリの姿を考え続けてみたい
最近は、さまざまな都市で、市民アプリをリリースしています。また、LINEで情報発信を一元化し、詳細を知りたい人はウェブサイトに誘導するという仕組みも増えてきています。そういったトレンドをしっかり考慮して、市民への広報のあり方を見直し、単に一律の情報を発信するのではなく、アプリを活用して受け手の属性や要望などを考慮した有用な情報を発信する姿勢を明確にすればよいと考えます。
子育て中の家庭には、子供が楽しめるイベントや、給付金などの案内をプッシュで配信する。(理想は、リンク先からシームレスに手続きまでできることですね)。住所を登録しておけば、近所の川が氾濫する可能性があるときに、しっかり注意喚起できるといった機能を持たせるといいと思うのです。
ただし、すぐに理想のアプリは完成しません。さまざまな市民のニーズをくみ取るために、ワークショップを開催する、アンケートも頻繁に取る、既存のアプリで活用できるものがないか棚卸する、といった地道な努力が必要です。これらの作業は行政だけでは難しいので、産官学の枠組みを機能させることが大切ですし、専門家としてITコーディネータが交通整理することも効果的です。
〇いい市民アプリができた!さあ、そのあとは?
今まで述べてきたようなアプリができれば、若者から中年層までは、アプリで生活に関する情報を取得できます。利用者も増えてくるでしょう。そうすると、市民向けの広報誌はアプリに移行していくことになります。アプリの閲覧が難しい人に対しては、引き続き広報誌を入手できるようにすればいいのです。郵送に切り替えてもいいでしょうし、かかりつけの診療所や公民館などで入手できるようにしてもいいでしょう。もちろん、学生などの力を借りて、アプリをインストールするとかサポートするという対応も効果的です。
そこまで環境が整ってくると、回覧板はデジタルに置き換えられる可能性も高まります。市民アプリを地域通貨等に紐づけることにより、自治会費や寄付金などの集約も容易になる可能性があります。
そういった省力化が進めば、自治会の役員のなり手も増えるかもしれませんし、地域行事の開催などにリソースを注ぐこともできます。
私は、三セクのまちづくり会社の仕事も担当していますが、以前、自治会の広報のデジタル化に関するワークショップを開催したことがあります。その時、子育て中の女性が出席されて、「子供の手を引っ張って、市役所の広報誌を配布するのは本当に辛い、どうにかならないか」と言われました。私は、市の仕事をしているわけではないので、なにも責任ある発言はできなかったのですが、少しずつでもいいので、行政の伝達や広報を紙からデジタルに変えるお手伝いをしたいと思っています。
ぜひさまざまな地域の産官学の皆さんが知恵を出し合って、そして、私たちITコーディネータが意見を集約して、市民がしっかり活用できる市民アプリの開発を提案できるとよいと思います。そして、市民の広報誌や回覧板の配達といった負担を軽減し、その余力で地域のつながりが強まるという成果を出したいと思うのです。
執筆者
浅野 卓(アサノタカシ)
Takashi Asano
所属
株式会社サーラビジネスソリューションズ 代表取締役社長
株式会社サーラコーポレーション 執行役員(グループDX推進 兼 地域関連事業 兼 監査部担当)
株式会社豊橋まちなか活性化センター 専務取締役
豊橋駐車場株式会社 取締役
公益財団法人東三河地域研究センター 監事
NPO)日本システム監査人協会 理事 同協会 中部支部副支部長 同協会 情報SEC監査研究会 座長
豊橋北ロータリークラブ所属(2023-24 職業奉仕委員長)
(前職)
豊橋ステーションビル株式会社 代表取締役社長
豊橋商工会議所 小売商業部会長
自己紹介・経歴
1967年生まれ 東京都出身 京都大学法学部、放送大学教養学部(情報、社会と産業、人間と文化コース)卒業 京都市在住
JR東海監査部長、同社子会社の豊橋ステーションビル株式会社代表取締役社長を経て、2025年2月より現職。その他、豊橋市関連のさまざまな役職に就いている。
内部監査、システム監査等の実務経験が豊富。現在は、サーラグループ全体のDX戦略の策定、グループ各社のデジタル化に取り組みつつ、これまでの職務経験やスキルを活かし、デジタル技術やさまざまなデータを活用した地域活性化の具体化にも取り組んでいる。
保有資格
•ITコーディネータ(DX認定サポータ)
•公認内部監査人(CIA)
•公認システム監査人(CSA) 他
講演実績
日本内部監査協会、ISACA名古屋、ITC京都・ちば、CSAフォーラム(日本システム監査人協会)
事業構想大学院大学、恵泉女学園大学、大正大学、中京大学、松本大学
東三河懇話会 (https://www.konwakai.jp/2024/07/16/salon477/)
他 多数