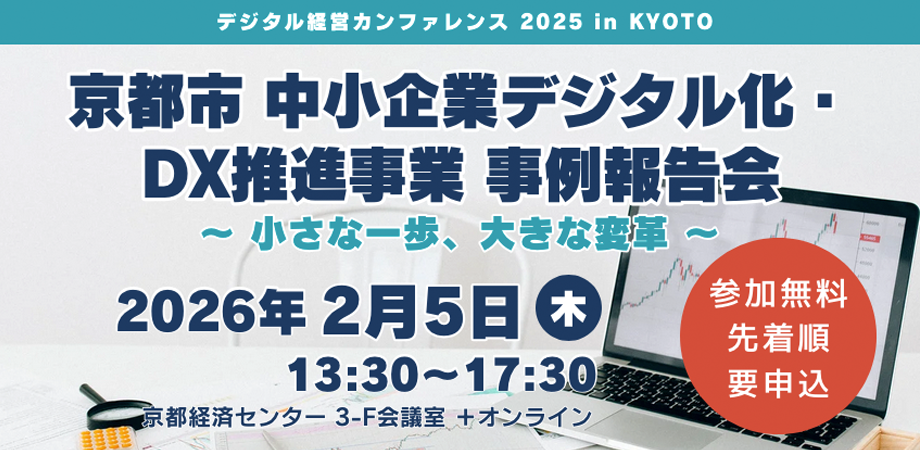皆さんこんにちは!
中堅・中小企業向けのDX推進のガイドである経済産業省の「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き2.1」が改訂され、『中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025』として新たにリリースされました。この改訂のポイントは以下の様に記述されています。(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chukenchushotebiki/dx-chukenchushotebiki.html)
• これまでの「DXの進め方」「DXの成功のポイント」を中心に記載して内容を簡潔にし、かつ、イラストを含めてわかりやすい手引きに刷新
• デジタルガバナンス・コード3.0の改訂を踏まえ、「DXの成功のポイント」を追記
• DXセレクション選定企業レポートを手引きに統合し、企業の取組事例を「DXの進め方」「DXの成功のポイント」に沿って紹介
今回は、このDX推進の手引きの内容をご紹介します。皆さまのDX推進のヒントとなればと思います。
DXの第一歩は「経営ビジョン」から
「DX」と聞くと、最新のITツールやAI導入をイメージし、「うちのような小さな会社には関係ない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、手引きでは、DXの本質は「顧客視点で新たな価値を創出するため、ビジネスモデルや企業文化の変革に取り組むこと」だと定義されています。単なるツールの導入ではなく、経営そのものの変革なんですね1。
ここが多くの経営者が陥りがちな誤りです。「AIを使ってみようか」「新しいシステムを入れてみようか」と、手段から入ってしまうと、結局何のためにやっているのかわからなくなり、中途半端に終わってしまいがちです。
そうではなく、まずは「何のためにDXをやるのか」を考えることが重要です。
「5年後、10年後にどんな会社になりたいか」という明確な経営ビジョンを描くことから始めましょう。このビジョンを逆算して、現状の課題を整理し、その解決策としてデジタル技術をどう活用するかを組み立てていくのです。
失敗を恐れず、まずは「身近なところ」から
「大きなビジョンを掲げても、何から手をつけていいか分からない…」と悩む方もいるでしょう。そんな時は、
まずは身近で、取り組みやすいことから始めて、小さな成功体験を積み重ねることをおすすめします。
手引きで紹介されているDXセレクションの企業事例にも、そのヒントがあります。
たとえば、廃棄物処理業の有限会社道環は、これまでの紙ベースの報告業務をスマートデバイスでデジタル化し、1日3時間もの時間削減に成功しました。建設業の株式会社池田組は、測量にドローンを活用することで、人力で1日かかっていた作業をわずか30分に短縮しました 。
こうした「小さな成功」は、従業員の皆さまがDXの効果を実感し、モチベーションを高めることにつながります。手書きの伝票をデジタル化したり、グループウェアを導入してスケジュール管理をしたり、といった身近な一歩からでいいのです。
このようにして得た知見を活かし、徐々に業務プロセス全体、そしてビジネスモデルの変革へと取り組みを拡大していくことが、DXを成功させる秘訣です。
こういった身近なところから成功体験を積んでいくという方法は、大手企業でも採用しています。旭化成さんのDX推進ロードマップがまさにそのような内容になっています。以前のコラムでご紹介しますので、あわせて参照してください。
経営者が「孤独」にならないために
DX推進には、経営者の強いリーダーシップが不可欠です。
しかし、中小企業の経営者は、時に「孤独」になりがちです。DXという未知の領域で、誰に相談したらいいかわからない、という方もいるのではないでしょうか。
そんな時こそ、外部の力をうまく活用しましょう。手引きでは、「伴走支援者の存在」が重要だと述べられています 。
ITベンダーやITコーディネーターといった専門家は、経営者と対話することで、自社の課題をあぶり出し、将来のビジョンを明確にする手助けをしてくれます。DXセレクションの事例にも、ITコーディネーターとの対話を通じてビジョンを明確化し、業務プロセスを大胆に変革した株式会社ヒサノの事例が紹介されています。
また、従業員の皆さまを巻き込むことも大切です。
株式会社後藤組では、現場社員自身がノーコードツールを活用して業務アプリを作成する「全員DX」を推進し、3,000件を超えるアプリが生まれたそうです。
従業員にDXの主体となってもらうことで、現場からの改善提案が活発になり、組織全体の変革につながります。
DXはコストではなく「投資」です
多くの経営者は、DXを「コスト」として見てしまいがちです。しかし、手引きは「DXに投じる資金をコストとして捉えるのではなく、重要な投資と位置付ける」ことの重要性を強調しています。
DXは、単に目の前の業務を効率化するだけではありません。
顧客接点やサプライチェーン全体を変革し、データを活用することで、新しい価値を創出する可能性を秘めているのです。
たとえば、株式会社eWeLLは、訪問看護の電子カルテで蓄積したデータを活用し、生成AIによる看護計画・報告書を自動作成するサービスを開発しました。これにより、看護師の業務時間を大幅に短縮し、看護師不足という社会課題の解決に貢献しています。
株式会社ヒバラコーポレーションは、自社工場のDXで得たノウハウを、他社向けのソリューション事業として展開し、新たなビジネスモデルを創出しています。
DXは、企業を持続的に成長させるために不可欠な取り組みです。
ぜひ、この手引きを参考に、皆さまの会社もDXの旅を始めてみてはいかがでしょうか。応援しています!
執筆者プロフィール
氏 名 宗平 順己(むねひら としみ)
所 属 武庫川女子大学共通教育部教授
ITコーディネータ京都 理事
Kyotoビジネスデザインラボ 代表社員
資 格 ITコーディネータ、公認システム監査人
専門分野
・デジタルトランスフォーメーション
・サービスデザイン(デザイン思考)
・クラウド
・BSC(Balanced Scorecard)
・IT投資マネジメント
・ビジネスモデリング
・エンタープライズ・アーキテクチャ などなど