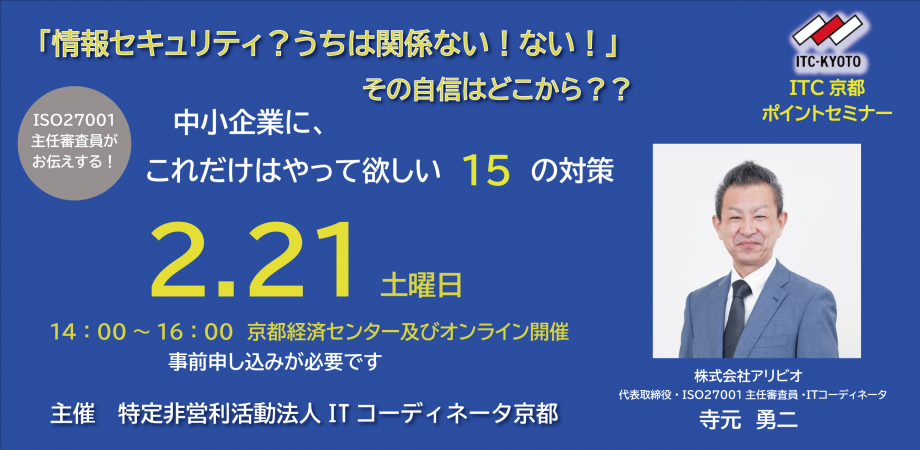~外注依存からの脱却と社内DX人材の育て方~
「DXを進めたいけれど、うちにはIT人材がいない」「システムのことは全部ベンダーに任せているから、社内では誰もわからない」こんな悩みを抱えている中小企業の経営者の方は多いのではないでしょうか。
しかし、ちょっと待ってください。本当に必要な人材がいないのでしょうか?中小企業のDX推進に必要な人材とは、どんな人材なのでしょうか。
今回は、多くの経営者が誤解している「DX推進に必要な人材」の本当の姿と、中小企業でも実践できる社内DX人材の育て方について、お話ししたいと思います。
「DX人材がいない」は本当か?
「DX人材」と聞くと、多くの経営者は「プログラミングができる技術者」「システムエンジニア」を思い浮かべるかもしれません。しかし、中小企業のDX推進に本当に必要なのは、そうした高度な技術者ではありません。
必要なのは「自社の業務をよく理解し、デジタルツールを使って課題を解決し、ビジネス変革を推進できる人材」です。
プログラマーのような「IT人材」とは異なり、「DX人材」はビジネスの視点を持ちながらデジタル技術を活用できる人材を指します。
そう考えると、実は社内にその”芽”はすでにあるかもしれません。Excelで関数を使いこなしている事務担当者、新しいツールに興味を持って自主的に調べている若手社員、業務効率化のアイデアをよく出してくれる現場のリーダー、ChatGPTをすでに使っている営業担当者、こうした方々こそ、社内DX人材の候補なのです。
なぜ今、社内DX人材が必要なのか
「システムのことは専門のベンダーに任せておけばいい」と考える経営者もいらっしゃるでしょう。確かに、専門的な技術は外部の力を借りるべきです。しかし、すべてを外部に丸投げしてしまうと、DXは実現しません。
なぜなら、DXは単なる「ツールの導入」ではなく、「ビジネスモデルや業務プロセスの変革」だからです。外部のベンダーは、あなたの会社の業務の細部や現場の課題を、あなたほど深く理解することはできません。
さらに、ビジネス環境の変化スピードが加速する現代では、「この業務を改善したい」と思ったときに、すぐに動ける体制が必要です。外部ベンダーとの調整に時間をかけていては、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまいます。
例えば、映像や音響機器の設計や施工を手掛ける、京都通信特機株式会社では、現場がノーコードツールを活用して業務アプリを作成する「DXはじめの一歩」を推進しています。これによりペーパーレスの実現と働き方改革に踏み出しています。
外注依存がもたらす3つのリスク
外部ベンダーへの過度な依存は、次のようなリスクを生みます。
リスク①:ブラックボックス化 システムの中身がわからず、ちょっとした改善やカスタマイズができない状態に陥ります。結果として、「使いにくいけど我慢するしかない」システムを使い続けることになります。
リスク②:コスト増大 小さな変更や追加機能の依頼でも、都度見積もりが必要で、想定外のコストが発生します。気づけば、初期投資よりも保守費用のほうが高くなっていた、というケースも珍しくありません。
リスク③:スピード低下 外部ベンダーとの調整、仕様の確認、開発、テスト……と、改善ひとつに数週間から数ヶ月かかってしまいます。その間に、市場環境は変わり、当初の課題感も薄れてしまうかもしれません。
例えば、小売業A社では、繁忙期前に在庫管理機能の追加が急遽必要になりましたが、ベンダーとの調整に時間がかかり、開発完了まで3ヶ月。また開発費用も高額になり、結局、繁忙期には間に合わず、人海戦術で乗り切るしかありませんでした。
こうしたリスクを回避するためにも、社内に「ビジネスとデジタル技術の橋渡し役」となるDX人材が必要なのです。
社内DX人材に求められる本当のスキルとは
では、社内DX人材には、どんなスキルが求められるのでしょうか。繰り返しになりますが、高度なプログラミングスキルは必須ではありません。むしろ、次のような複合的なスキルが重要です。
業務理解力 自社の業務プロセスや課題を深く理解していること。現場の「困りごと」を言語化できる力が必要です。
デジタルツールの活用力 最新のデジタルツールの情報を収集でき、基本的な活用方法を理解していること。ただし、すべてを知っている必要はありません。「わからないことを調べる力」があれば十分です。
コミュニケーション力 経営層、現場、外部ベンダーの間を”翻訳”できること。それぞれの立場や言葉を理解し、つなぐ役割を果たせる人材が理想です。
柔軟性と学習意欲 新しいツールや手法を積極的に学べる姿勢。「失敗してもいいから、まずやってみよう」というチャレンジ精神が大切です。
こうしたスキルは、特別な才能ではありません。育成によって十分に伸ばすことができるのです。
中小企業でもできる!実践的な育成ステップ
それでは、具体的にどのように社内DX人材を育てていけばよいのでしょうか。3つのステップでご紹介します。
ステップ1:「DX人材の候補」を見つける・育てる
まずは、社内で候補となる人材を探しましょう。探すべきは、次のような特徴を持つ人です。
|
特に、プログラミングに興味がある人材は、貴重な存在です。「学生時代に少しやった」「独学で勉強してみたい」という程度でも構いません。そうした芽を見つけたら、ぜひ育成の対象として声をかけてみてください。
年齢や役職にこだわる必要はありません。むしろ、若手や現場スタッフのほうが、柔軟な発想で取り組んでくれることもあります。
具体的な発掘方法としては、次のようなアプローチが有効です。
|
そして候補者を見つけたら、こんな風に声をかけてみましょう。
|
「○○さん、いつもExcelを工夫して使ってるよね。実は今、会社全体で業務改善プロジェクトを始めようと思っていて、○○さんの力を借りたいんだ。一緒にやってみない?」 |
選んだ人材に「なぜあなたを選んだのか」を明確に伝え、動機づけすることが重要です。「あなたの力が必要だ」というメッセージは、本人の意欲を大きく高めます。
ステップ2:小さな成功体験を積ませる
育成の鍵は、「小さな成功体験」を積み重ねることです。いきなり大きなプロジェクトを任せるのではなく、身近で効果が見えやすい課題から始めましょう。
たとえば、次のようなテーマが適しています。
|
こうした取り組みには、ノーコード・ローコードツールが非常に有効です。プログラミングの知識がなくても、直感的な操作で業務アプリを作ることができます。
業種別の具体的な成功事例をいくつかご紹介しましょう。
製造業の例:出荷検品チェックリストのデジタル化 従来は紙のチェックリストに手書きで記入していた検品作業を、Google App Sheet を使ってスマートフォンアプリ化。記入ミスが8割削減され、検品履歴の検索も瞬時にできるようになりました。
小売業の例:在庫確認作業の効率化 倉庫内の在庫確認をZaicoというスマホアプリを使い、棚卸作業の時間が半減。リアルタイムで在庫数を把握できるようになり、発注精度も向上しました。
飲食業の例:予約管理の自動化 電話とノートで管理していた予約を、Google カレンダーを使った予約システムに移行。お客様が直接予約でき、スタッフの電話対応時間が7割削減されました。
サービス業の例:顧客対応履歴の一元管理 バラバラに管理されていた顧客からの問い合わせ履歴をSLACKで一元化。誰がどんな対応をしたか全員が把握でき、対応品質が向上しました。
生成AIを活用したプログラミング加速の実例
さらに、生成AI(ChatGPTやGemini)を活用すれば、プログラミングのスピードを劇的に加速できます。
たとえば、営業部門で毎月手作業で行っていた売上集計を自動化したい場合、こんな風にChatGPTに依頼します。
|
プロンプト例: 「Googleスプレッドシートで、A列に日付、B列に商品名、C列に金額が入力されています。このデータから月別・商品別の売上集計を自動で行い、グラフを作成するGoogle Apps Scriptを書いてください」 |
すると、数秒で実用的なコードが生成されます。プログラミング経験が浅い人でも、生成されたコードをコピー&ペーストするだけで動くことがほとんどです。エラーが出ても、エラーメッセージをChatGPTに見せれば、修正案を提示してくれます。
実際の効果:
手作業での集計:毎月2時間
自動化後:ボタンを押すだけで5分
年間で約24時間の削減、つまり丸3日分の時間を生み出すことができました。
このような成功体験が、本人の自信とモチベーションを大きく高めます。「自分にもできた!」という実感が、次の挑戦への原動力になるのです。
( 私自身も、生成AIを活用した開発の記録を公開しています。https://note.com/mtb_ai )
ステップ3:改善活動として全社で取り組む文化をつくる
DX人材育成を特定の担当者だけの仕事にしてはいけません。むしろ、全社的な「改善活動」として位置づけることが重要です。
製造業では、カイゼン活動やQCサークルといった改善文化が根付いています。同じように、「業務をデジタル技術で改善する活動」を全社で推進するのです。
改善発表会の具体的な運営例をご紹介します。
ある運送業C社では、次のような取り組みを行っています。
|
この取り組みを始めて半年後、営業部の顧客管理改善が製造部に波及し、同じツールを使った生産管理への応用が生まれました。さらに経理部が請求書管理に展開するなど、改善の連鎖が起きたそうです。
改善活動のポイントは、失敗を責めないことです。「やってみたけどうまくいかなかった」という報告も歓迎し、「次はこうしてみよう」と前向きに捉える文化を作りましょう。
この手法は、清掃業や小売業、飲食業、サービス業など、業種を問わず有効です。「うちは製造業じゃないから」と諦める必要はありません。どんな業種でも、業務改善の余地は必ずあります。
京都通信特機株式会社の「DXはじめの一歩」も、まさにこうした組織文化づくりです。経営者が旗を振り、従業員全員がデジタルツールを活用する風土を作ることで、様々な改善アプリを作り出そうとしています。
また、外部の専門家を”賢く”活用することも忘れずに。ITコーディネーターや専門家の伴走支援を受けながら、一緒に学ぶ姿勢が成功のカギです。外部の目線が入ることで、社内では気づかなかった改善点が見えてくることもあります。
経営者が絶対にやってはいけない3つのこと
ここで、DX人材育成を失敗させる典型的な「経営者のNG行動」を3つお伝えします。
NG①:現場任せにして、経営者が関与しない 「DX担当者に任せておけばいい」と考えるのは危険です。経営ビジョンとの接続が切れ、単なる業務効率化で終わってしまいます。経営者自身が関心を持ち、方向性を示すことが不可欠です。
NG②:短期的な成果を求めすぎる 人材育成には時間がかかります。「3ヶ月で結果を出せ」といった短期的なプレッシャーは逆効果です。失敗を許容し、長い目で育てる姿勢が大切です。
NG③:育成した人材を単なる「システム担当」に固定化する せっかく育てたDX人材を、単なるヘルプデスクやトラブル対応係にしてしまってはもったいない。本来の役割は「ビジネスとデジタル技術の橋渡し役」であり、経営課題の解決に積極的に関わらせることが重要です。
例えば、ある卸売業D社では、社長が「DXは若手に任せた」と完全に丸投げした結果、各部署が独自にツールを導入しすぎてデータが分断。顧客情報が3つのシステムに散らばり、かえって非効率になってしまいました。経営者が全体像を描き、方向性を示すことの重要性を痛感したそうです。
また、建設業F社では、DX人材として育成した社員が、いつの間にか「パソコンの修理係」「プリンターのトナー交換係」になってしまい、本来の業務改善に時間を割けなくなってしまいました。経営者が明確に役割を定義し、守ることが重要です。
DX人材育成は「投資」である
社内DX人材の育成には、時間もコストもかかります。しかし、それは「コスト」ではなく、企業の競争力を高める「投資」です。
外部ベンダーへの依存を減らし、変化に素早く対応できる体制を作る。従業員が自ら考え、改善する文化を醸成する。こうした取り組みは、確実に中長期的なリターンをもたらします。
「うちには無理」と諦める前に、まずは社内の”IT好き”や”プログラミングに興味がある人”を探してみませんか?そして、小さな成功体験を積ませることから始めてみてください。
改善活動として全社で取り組めば、あなたの会社にも「全員DX」の文化が根付くはずです。
ITコーディネーター京都では、外部専門家として御社を支援し、一歩ずつ進めるお手伝いをしていきます。
執筆者プロフィール
山口 透(やまぐち とおる)
ITコーディネータ京都 理事
株式会社 エムティブレイン 代表取締役
デジタル変革(DX)と生成AIを活用したコンサルティングを手掛ける。中小企業から大企業まで、経営とITの架け橋として幅広くサポート。生成AIやIoT、デジタル化を活用したDX推進に強みを持ち、業務効率化やマーケティング戦略の革新を実現。+DX認定試験の問題作成プロジェクトリーダーとして、DX人材育成にも尽力。AIセミナーの企画・運営を通じ、企業のAIリテラシー向上に貢献。関西学院大学と大阪経済大学の中小企業診断士養成課程でデジタル化の授業を行っている。中小企業診断士、ITコーディネータ、システムアナリスト。著書に「ITコンサルティングの基本」(共著)他。