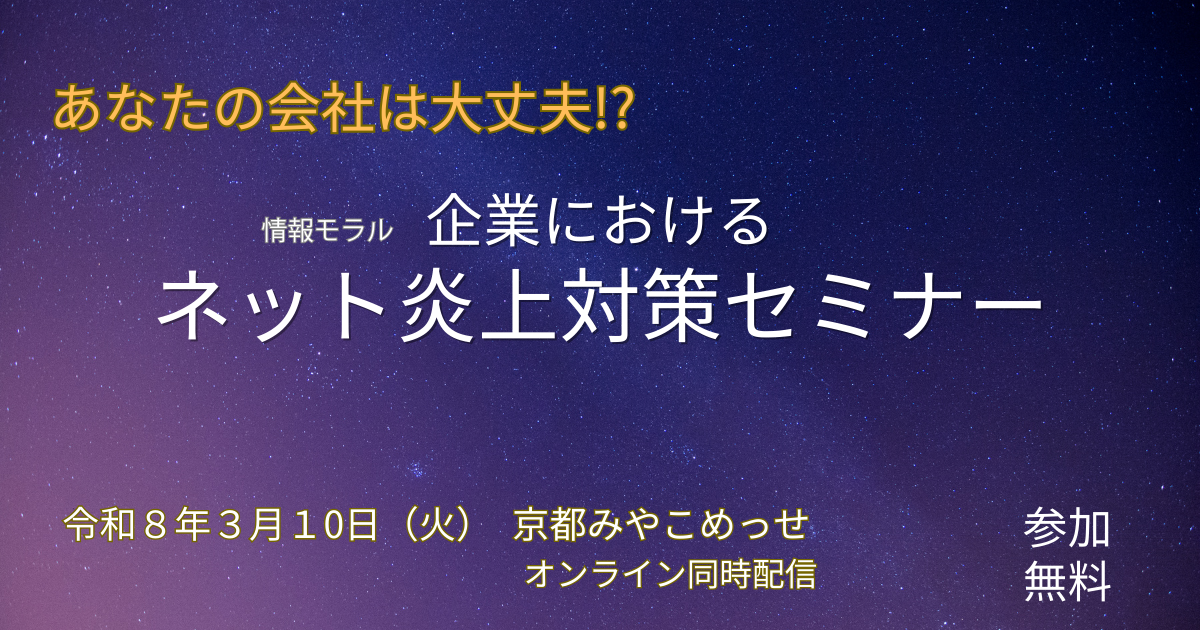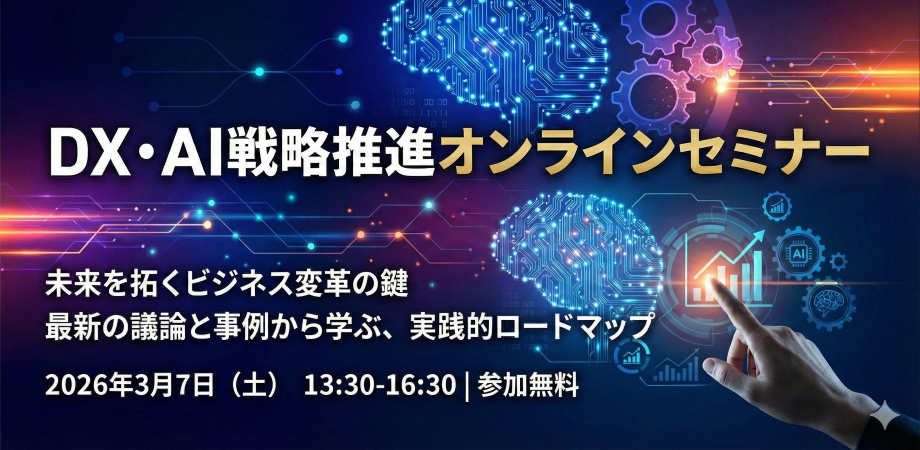最近、「AIの進化でコンサルタントは不要になるのでは?」という話を耳にすることが増えた。確かに、AIは膨大な情報を分析し、戦略のヒントを提示してくれる。だが、先日受講したITコーディネータのケース研修インストラクター養成研修を通じて、私はむしろAI時代だからこそ、ITコーディネータ(ITC)の存在価値が高まると確信した。
ITCの役割は、IT導入を支援する技術屋ではなく、経営変革を導く伴走者である。特に印象に残ったのは、DX推進という抽象的でつかみづらいテーマを、ITCプロセスに沿って進めることで“具体的な行動”に落とし込めるという点だ。
多くの企業でDXが進まないのは、「何から始めればいいか」が不明確だからだ。AIを使えばデータ分析や文書作成は容易になるが、「どこに向かうべきか」という根本的な問いはAIが決めてくれるわけではない。そこを明らかにするのが、まさにITコーディネータの仕事である。
研修で改めて腹落ちしたキーワードが三つある。「変革構想書」「価値実現サイクル」「成熟度」だ。
特に変革構想書は、企業が目指す“ありたい姿”を言語化し、全体の道筋を描くための重要な出発点となる。これがあることで、AI活用や業務改善といった個別の取り組みが、“点”ではなく“線”としてつながっていく。
価値実現サイクルは、その構想を具体化し、実践と検証を繰り返す仕組みだ。そして成熟度の概念は、自社の現状を客観的に捉え、どの段階で何をすべきかを判断するための“座標軸”を与えてくれる。
印象的だったのは、研修中に「外部環境や業界情報の収集にAIを積極的に活用すべきだ」と講師が強調していたことだ。AIは確かに有効な情報収集ツールであり、仮説検証を支援する心強いパートナーになる。だが、そのAIが出してくる“答え”をどう読み取り、どのように経営戦略に結びつけるかは、人の経験と文脈理解が欠かせない。AIはあくまで「支援者」であり、意思決定の本質は人間に残る。ここに、プロセスを理解しているITCの真価がある。
私の支援先でも、「DXを進めたいが、どこから手をつけていいか分からない」という声が多い。そうした企業こそ、まずは変革構想書を作り、全体を俯瞰した上で戦略仮説を立ててみることを勧めたい。
AIを活用することで情報収集や分析のスピードは上がるが、方向性を見誤れば効率よく迷走するだけだ。プロセスガイドラインに基づいて戦略を構築し、仮説検証を繰り返す――その地道なサイクルこそが、DXを“実行可能な戦略”へと変える鍵になる。
では、AI時代にITコーディネータがさらに価値を発揮するためには、何をすべきか。私は次の三つを提案したい。
① 変革構想書で“森”を見る:個別課題に飛びつく前に、ありたい姿を描き直す。
② AIを“共創パートナー”として使う:情報を丸投げするのではなく、AIの提案を人が吟味し、問いを深める。
③ フィードバックを大切にする:小さな仮説検証を重ね、柔軟に戦略全体へ反映していく。
AIの発展で、情報の非対称性は急速に解消されつつある。誰でもデータを得られる時代だからこそ、「正しい問いを立て、価値を実現するプロセス」を設計できる人が求められている。
ITコーディネータは、その設計図を描ける数少ない専門家だ。AIを敵ではなく味方にし、経営変革のプロセスを回すことで、私たちはこれまで以上の付加価値を生み出せる。
AI時代にこそ、ITコーディネータの活用を――それが、これからのDXを本当に前に進める力になる。
■執筆者
高橋幸司(タカハシ コウジ)
Koji Takahashi
所属
株式会社 東洋 常務執行役員
NPO)ITコーディネータ協会 理事
NPO)ITコーディネータ京都 理事
キャリア
25年以上にわたりIT業界でキャリアを積んできました。ネットワークエンジニアとしてのキャリアをスタートさせ、数多くの中小企業に対しネットワークやサーバーの設計・構築を行い、その後はセキュリティエンジニアとして、様々な事業者に対するセキュリティ対策を担当しました。さらに、クラウドエンジニアとしてAWSの設計・構築、DevOps環境の構築、SaaSインテグレーションなどを手がけてきました。また、FileMakerなどのローコード開発ツールを利用した開発も行ってきました。現在は、上記スキルに加えITC京都およびITCA(ITコーディネータ協会)の理事として、企業支援や教育活動にも尽力。多数のIT関連資格を保有し、幅広い知識と経験で企業のIT戦略をサポートしています。
保有資格
• ITコーディネータ
• 中小企業診断士
• ITストラテジスト
• 公認情報セキュリティ監査人
• 情報処理安全確保支援士
• 米国PMI認定PMP