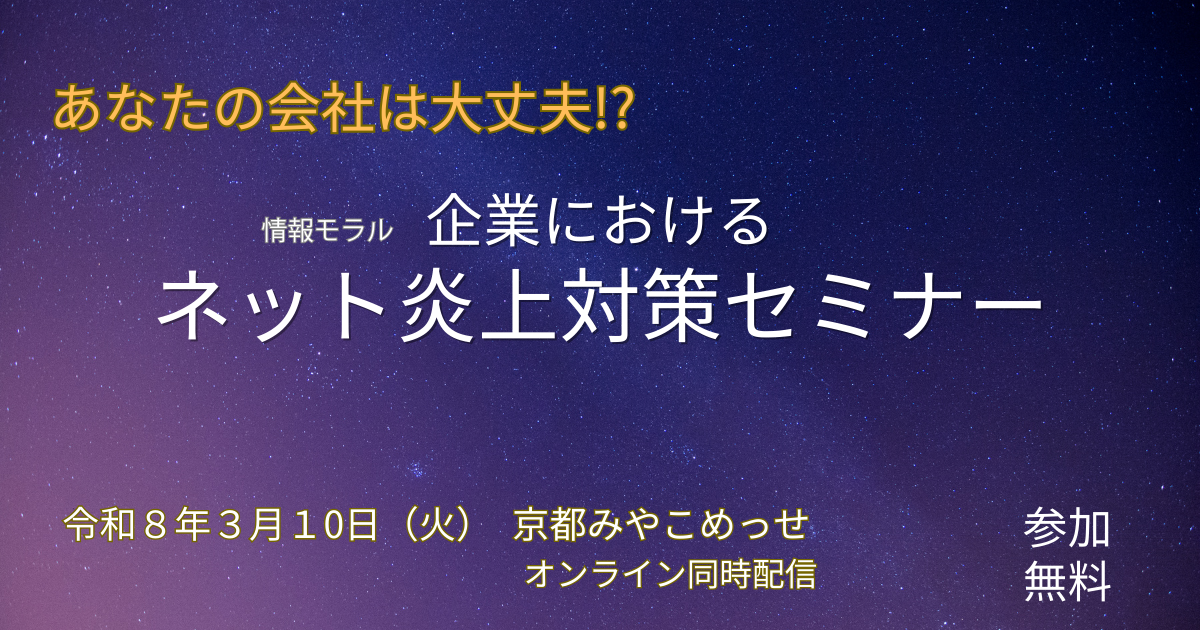経営支援の場では、フレームワークが実務のなかで自然に使われています。ITコーディネータが行う上流の課題抽出にも用いられますし、経営陣やマネージャの皆さんも活用されている場面があることでしょう。そして、経営の階層だけでなく、生産から販売まで、多くの分野で様々なフレームワークが用いられています。
経営だけでなく、他の領域でも同様の整理法が使われているようです。例えば医療の領域でも、問診の習得過程でフレームが用いられると聞きます。命に直接関わる医療と経営とを同列に扱うことはできませんが、「フレーム=型を仮置きして理解を進める」というプロセスには共通点があるように思えます。
大切なのは、こうしたフレームを適度な距離感で扱うことなのかもしれません。
経営分野では、フレームワークは戦略策定そのものではなく、議論を共通化するための道具として発展してきました。企業の多角化が進み、意思決定が複雑化するなかで、図式やマトリックスによって考え方を揃える試みが広がり、それが教育や実務の中で定着していきます。フレームは理論というより、チームで思考を共有するための仕組みとして機能してきたと言えます。
ちなみに、医療分野では問診の整理法があるものの、近年の問診AIや医療AIの解説においては、そうしたフレームの名称が前面に出てこないことも多いようです。フレームが使われていないというより、設計や対話の中に吸収され、あえて見せない形で働いているのかもしれません。経営支援の現場の実感に引き寄せてみると、そんなふうに考えられます。
支援の現場では、一定の枠組みを意識しているはずなのに、会話そのものは自然に進み、型を使っていることが表に出ないという聴き取りをすることが多くあります。支援の場ではフレームを強調するよりも、理解の流れを整えることを優先するからです。
日々の経営の現場でも、同様の場面がしばしば見られます。会議の場での「まず現状を整理しよう」「数字の話と人の話を分けて考えよう」といった投げかけ。現場では情報が入り混じりやすく、売上の話が人材の話へと移り、設備や市場の不安が同時に語られることも少なくありません。そのようなとき、話題の位置を整えるだけで、意思決定の見通しは大きく変わります。
近年は、こうした整理の作業に生成AIを取り入れる場面も増えてきました。フレームワークをAIに任せるというより、人が丁寧に聴き取った具体的な内容を、あとから構造的に見直すための補助として使う感覚に近いはずです。ヒアリングのメモや断片的な議事録をもとに、話題を並べ替えたり、重なっている論点を分けたりする作業は、これまで人が時間をかけて行ってきたものです。生成AIは、その下書きを短時間で用意する手助けをしてくれます。
そのとき、最初からAIに問いを委ねてしまうと、会話が整いすぎてしまい、現場の細かなニュアンスがこぼれ落ちることもあります。これは、SWOTを使い慣れてくると、よく整理されているものの実践には弱い結論に落ち着いてしまう現象にも少し似ています。皆さんにも覚えがあるのではないでしょうか。
フレームワークは会話の最初に持ち出すよりも、後から輪郭を整えるために使うという現場感覚をお持ちの方も多いと思います。具体的な事象を人が丁寧に聴き取り、その後でAIを使って構造を整えるという順番が大切です。
経営者やマネージャーにとって、フレームワークや生成AIを用いる手順を整理して現場に臨むこと。それが、こうしたツールとの適切な距離感の把握にもつながるはずです。
[補足]
ビジネスフレームワークの変遷について(概観)
前史:フレームが求められた背景(1950〜60年代)
戦後の高度成長期、企業は多角化や海外進出を進め、事業部制の導入も広がりました。意思決定は急速に複雑化し、それまで中心だった経験や勘、経営者の直感だけでは議論が共有しにくくなります。その結果、「誰が見ても同じ議論ができる共通言語」として、思考を整理する枠組みが求められるようになりました。
第1期:ポートフォリオ思考の登場(1960〜70年代)
多角化企業の増加に伴い、「どの事業に投資すべきか」という問いが重要になります。ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が提示した事業ポートフォリオの考え方は、複雑な経営判断を二軸の図式として整理する試みでした。ここでフレームは、意思決定を支える“図”として広く知られるようになります。
第2期:構造分析フレームの広がり(1980年代)
オイルショック以降、国際競争や価格競争が激化し、企業は「なぜ利益が出るのか」を説明する必要に迫られました。競争戦略論やバリューチェーンなど、構造的に企業活動を捉える枠組みが広まり、フレームは戦略策定の補助だけでなく、環境理解のための視点として用いられるようになります。
第3期:思考の再現装置としてのフレーム(1990年代)
コンサルティング業界では、若手でも一定水準の分析ができるようにするため、MECEやIssue Treeなどの思考法が体系化されました。フレームは理論というより、思考を再現可能にする教育ツールとして広がっていきます。
第4期:現場への広がりと民主化(2000年代〜)
IT化やスタートアップ文化の広がりとともに、Business Model CanvasやKPIツリーなど、現場で使いやすいフレームが増えていきました。経営が専門家だけのものではなくなり、フレームは実務者の日常的な道具へと変化します。
第5期:暗黙知としてのフレーム(2010年代〜)
熟練者ほどフレームを使っていないように見える場面が増えます。これはフレームが消えたのではなく、思考の基盤として内在化した結果とも考えられます。ヒアリングや会話の中で自然に使われながらも、表には現れにくくなりました。
現在:生成AIとの関係
近年の生成AIは、フレームそのものを教えられていないにもかかわらず、構造的な整理を行うことがあります。これは、人間がフレームを用いてきた対話の蓄積を学習しているためとも考えられます。その結果、フレームを明示的に使う方法と、自然な対話の中で構造を浮かび上がらせる方法のあいだで、実務のあり方が改めて問い直されつつあります。
関連文献(参考)
・保健医療分野における生成AIの国内外利活用事例の把握及び利活用可能性の探索のための研究
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/download_pdf/2023/202306038A.pdf
・医療におけるAIエージェントの基礎アーキテクチャ
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666379125004471
◆執筆者プロフィール
松井宏次(マツイ ヒロツグ)
ITコーディネータ京都 会員
中小企業診断士 ITコーディネータ 健康経営エキスパートアドバイザー