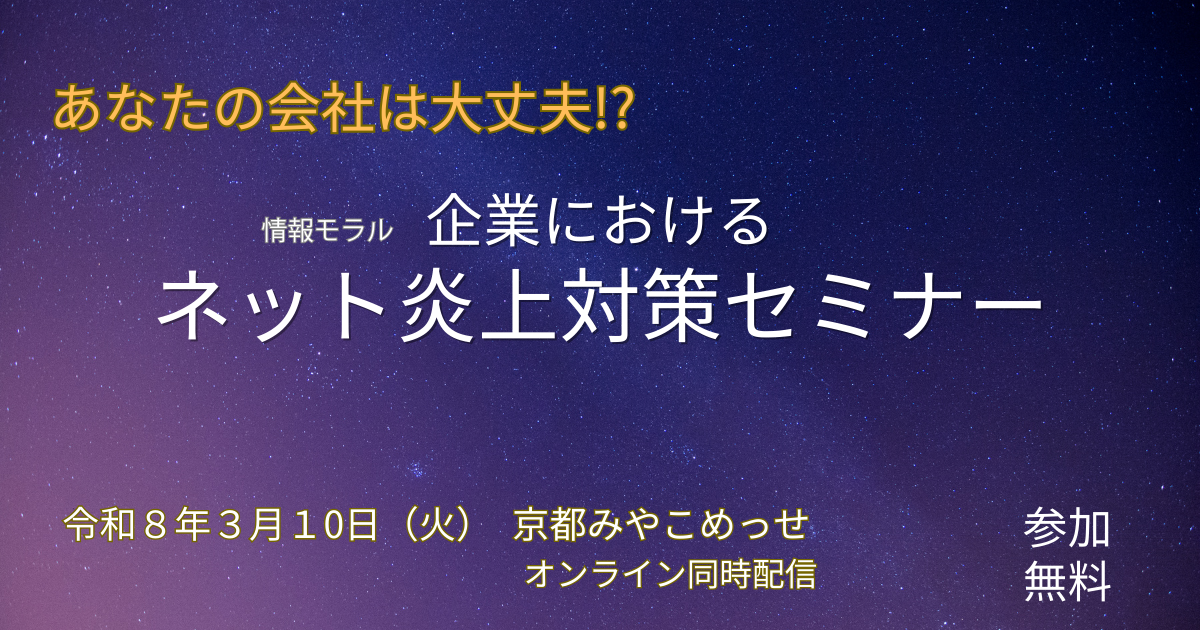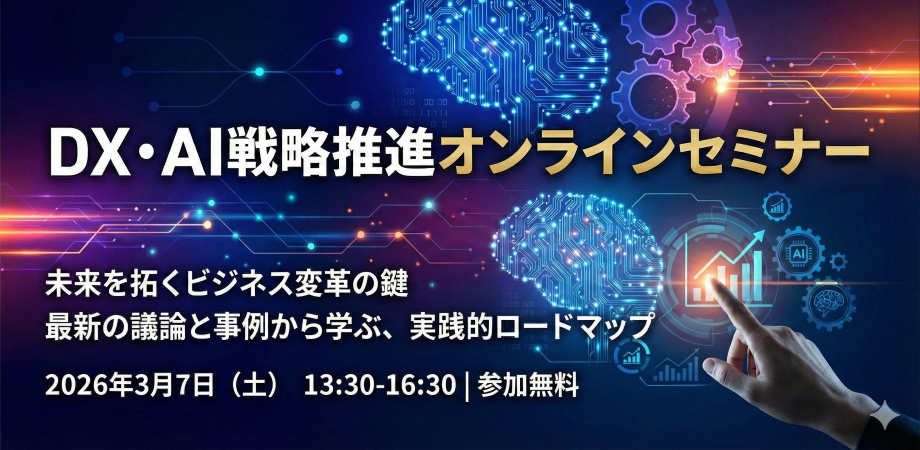11/2(日)ITC京都生成AI勉強会_WEB/SNS研究会 10月例会を開催しました。
今回も20名を超える多数の方にご参加いただきました。
前半は、ITC京都理事の山口さんに「中小企業のDX/ITにおける生成AI活用の実態と課題」をテーマに、ご自身の活動と現場での具体的な事例を共有いただきました。
生成AIの活用事例
中小企業の現場で実際に行われている生成AIの活用例として、次のような取り組みが紹介されました。
需要予測・在庫管理の効率化
AIを活用して在庫の偏りや発注ミスを防止し、現場判断を支援。マニュアル作成の自動化
現場スタッフの説明内容をAIが自動で文章化し、マニュアル整備を効率化。品質管理の改善支援
AIが品質チェック項目を見直し、改善活動を再活性化。業務自動化(VBAなどの生成)
生成AIによるスクリプト作成で、日常業務の効率化を実現。
これらの事例は、「小さく始めて成果を積み重ねる」という現場主導のアプローチとして紹介されました。
現場で見られる課題
一方で、AI導入を進める上では次のような課題も共有されました。
目的の誤解:「AIがモノづくりを代行する」と誤解され、導入を断念する例。
信頼性への不安:「誤った情報を出されると困る」という現場文化の壁。
データ不足:AI活用の前提となる定量データ・記録が不足。
変革への抵抗:「うちは特殊だから」と外部事例を取り入れにくい風土。
課題解決へのアプローチ
こうした課題に対し、参加者と意見交換しました。
知識共有の仕組み化:個人利用から法人契約への切り替えにより、AIナレッジを社内に蓄積。
自動化の徹底:生成AIで作成したプログラムを使い、標準業務を自動化して信頼性を高める。
データ文化の定着:まずはスプレッドシートなどを使い、日常業務データを記録・蓄積する意識づけから始める。
後半ワークショップ:新しいAIツールの紹介
後半は、積さんから最新のAIツール群が紹介されました。
-
データ統合プラットフォーム
「Genspark Hub」や「Fello LiveDoc」など、社内資料やURLを読み込み、AIに質問・要約・分析をさせるツール。
複数の文書を横断的に扱えるため、社内データの活用範囲を大きく広げます。 -
AIブラウザーの進化
「Atlas」「Genspark Browser」など、Web上の情報収集・メール返信・SNS投稿を自動で代行できるAIエージェント搭載ブラウザーが登場。
特にOpenAIの「Atlas」はエージェント機能が非常に強力で、業務効率化が大きく期待できそうです。