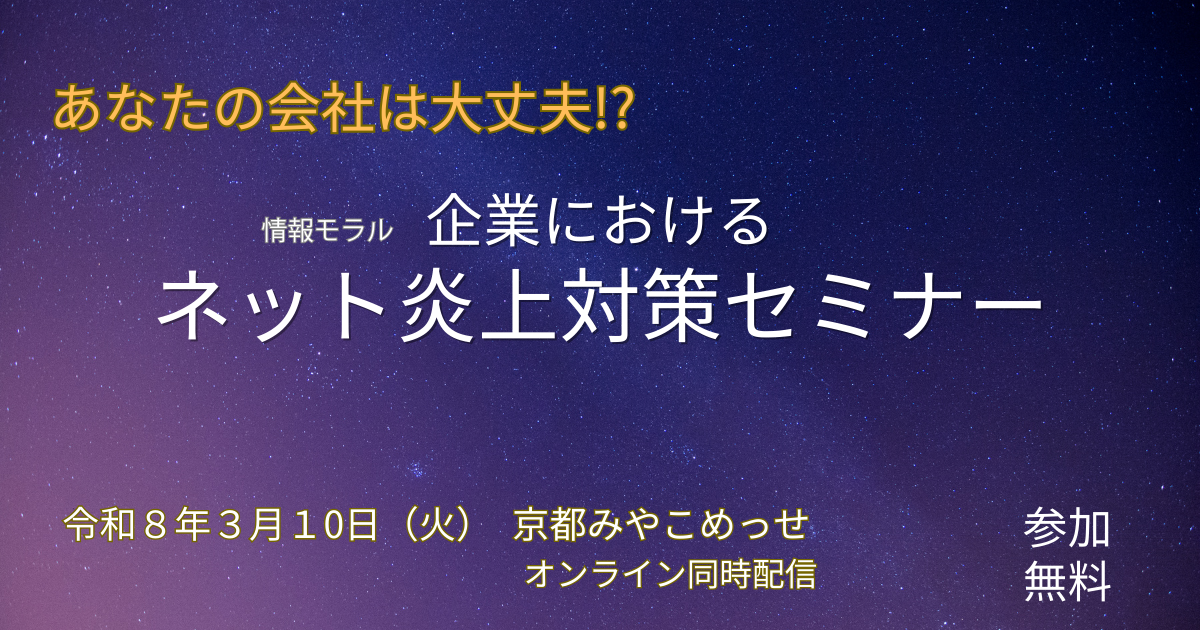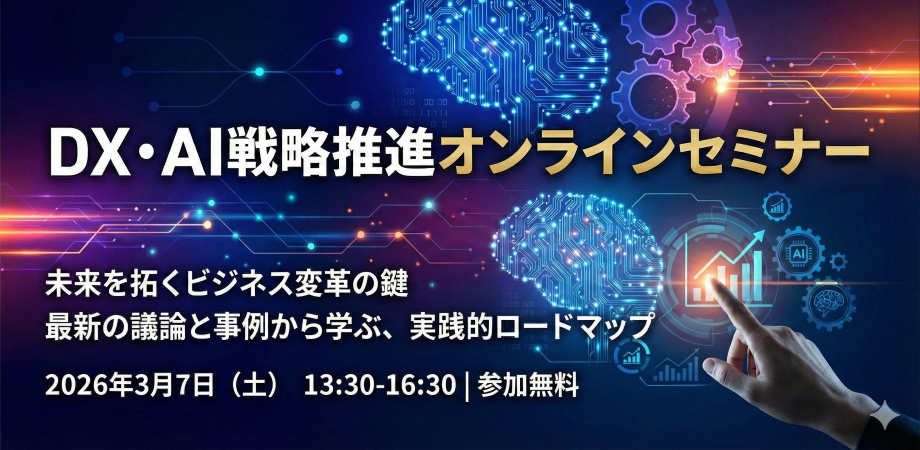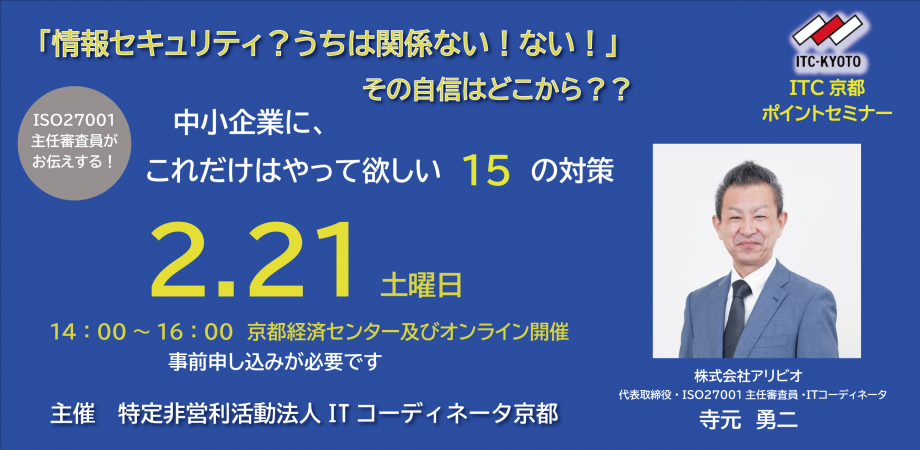●すべての企業は商売をしている
世の中にはいろいろな業種があります。たとえば、製造業。製造業とはどのような業種でしょうか。言葉通り、製品を造ることが仕事です。実際、製造業で働く人たちは、自分たちはものづくりをしていると思っているでしょう。建設業はどうでしょう。たぶん何らかの建築物を建てるのが仕事と思っているに違いありません。しかし、ここで少し考えてみる必要があります。企業はすべからく商売をしているのではないでしょうか。確かにものとづくりをしている。建物を建てている。それに違いはないのですが、結局、それでもって商売をしているのではないか。企業経営者やそこで働く人たちは、すべからく商売人ではないのか。
●「売る」がすべての核心
言い換えればこういうことです。企業の中心的営みは、「売る」ことである。製造業では、多くの場合常に良いものを造ろうと努力されているでしょう。しかし、自分たちがどれだけ良いものだと思っていても、もし、それが全く売れなかったらどうなるでしょう。もちろん、在庫の山です。早晩倒産するでしょう。建設業でも、いくら自分たちは高品質の建物を建てられると思っていても、1件の受注もなければ、建てることさえできないでしょう。やはり会社は存続できないでしょう。売れなければ、話にならないのです。よって、製造業であっても中心はものづくりではありません。「売る」ことです。建設業であっても、何業であっても、売れなければ会社の存続もおぼつかない以上、中心は「売る」ことなのです。
では、「売る」とはどういうことでしょうか。簡単です。顧客が買ってくれるということです。顧客が「欲しい」と思い、お金を払ってくれることです。この、お金を払うということが、なかなかのハードルなのです。ショッピングモールを歩いているといいなあと思うものがあります。これはすてきだとか、便利そうだとか、おいしそうだとか、いろいろいいなあと思います。しかし、そのすべてにお金を払う人はいません。その中でも、どうしても必要なもの、どうしても欲しいものだけにお金を払うのです。顧客がお金を払うとは、その意味で簡単なことではないのです。顧客にとって価値があるということは、お金を払うかどうかで明確になります。自社の商品に対して「なかなかいいですね」とは言ってくれるが、お金を払ってくれないとするなら、それはその顧客にとっては価値がないと同義です。お金を払ってでも欲しいと思う場合だけ、顧客が価値を認めたということになるのです。
価値があるということは、顧客の切実な(お金を払ってでも解決したい)課題を解決するということであり、顧客の状況を何らかの意味でよりよくすることに役立つということであり、さらに大きく言えば世の中をよりよくすることに役立つということなのです。その場合にのみ、支払いが発生し、お金が動き、売上や利益になる。企業活動の中心は顧客が買ってくれることであり、よって企業側から見れば「売る」ことなのです。なので、顧客にとって価値あるものを売ることが企業活動の核心中の核心です。極端な言い方かもしれませんが、商品をどう調達するかは本質的な問題ではありません。自社で製造しようが、他から仕入れようが、顧客が心底ほしいものを売ることができれば、それでいいのです。(もちろん、どこからも仕入れられないような独自なものを売ろうとすれば自社で製造する以外ないですし、造った方が高利益率になるという場合も自社で製造するということになります。しかし、逆に言えば、そういう明確な事情があるので造るのであって、そうでなければ、商品の調達方法は本質的な問題ではないのです。)
●すべてを「売る」から始める
顧客がお金を払ってくれなければ売上も利益も上がらず、企業は存続できません。企業の側から言えば、「売る」ことがその存亡を決定づけます。とすれば、企業のビジネスプロセス、業務プロセスの中心は「売る」ことにあります。つまり、ビジネスプロセスも業務プロセスも、「売る」ことを起点として設計されていなければならないのです。製造業の場合、結構製造部門が強くて、とりあえずいいものを造ったからあとは営業が売ってきてくれと言わんばかりのことがよくあります。しかし、これではプロセスが逆です。まず「売る」から始めるのです。つまり、何が売れるのか、何が顧客の切実な課題を解決するのか、何ならば顧客は喜んでお金を払ってくれるのか、それを徹底的に考え抜くところから始めなければなりません。それが見えてきたら、それを具体化した商品やサービスの設計に入り、その製造プロセスの設計に入り、そうして初めて実際の製造に入ることになる。この順番でなければ「売る」ことを中心にしていることにはなりません。
●「売る」を中心としたビジネスプロセス
ビジネスプロセスとはビジネスのプロセスである以上、顧客に「価値」を「売る」ためのプロセスのはずです。しかし、明確にそのように設計されている中小企業は少数ではないかと思います。中小企業には長年続けてきた既存事業があります。長年続けてきているので、お得意様も、仕入先も、ある程度までは確立されており、いわばルーティン化されていることがままあります。そうなると、深く考えなくても日々の仕事は回ります。確かに顧客は買ってくれるが、そもそも自分たちの商品は顧客のどのような課題を解決しているのか、顧客は何にお金を払ってくれているのか、そもそも自分たちの商品の何が価値なのか、そうしたことをほとんど考えなくてもすべてが回っていくのです。それで向こう10年、20年、30年と何の不安もなくやっていけるなら、それでもいいかもしれません。しかし、私がお聞きする範囲でも、経営者は将来に大きな危機感を持っておられます。であれば、あらためて、自分たちがどんな価値を提供しているのか、そして、10年、20年、30年と持続的に成長していくために、今後どのような価値を提供していけばいいのか、それを徹底的に考えていく必要があるのではないでしょうか。
「売る」が中心にあってはじめてビジネスは成り立ちます。ビジネスが成立していてはじめてビジネスプロセスが設計できます。ビジネスプロセスがあってはじめて業務プロセスが設計でき、それによってはじめて作業プロセスが設計できます。マーケティングと言いますが、マーケティングとは企業のすべてのプロセスを「売る」を中心に設計しなおすことだと思います。そのとき、一つ一つの作業、一つ一つの業務が、直接、間接に、すべて「売る」につながり、顧客の「買う」につながり、顧客の課題解決につながり、顧客の、世の中の役立ちにつながるのです。
◆ 執筆者プロフィール
清水 多津雄(しみず たつお)
CPC創発経営研究所 代表
ITコーディネータ
企業の情報システム部門でITマネジメントに従事したのち、イノベーションマネジメントに取り組み、創発的な経営方法を研究。2018年CPC創発経営研究所を設立。2020年「創発経営」で商標登録。現在、創発経営に基づく中小企業の経営サポートに従事している。