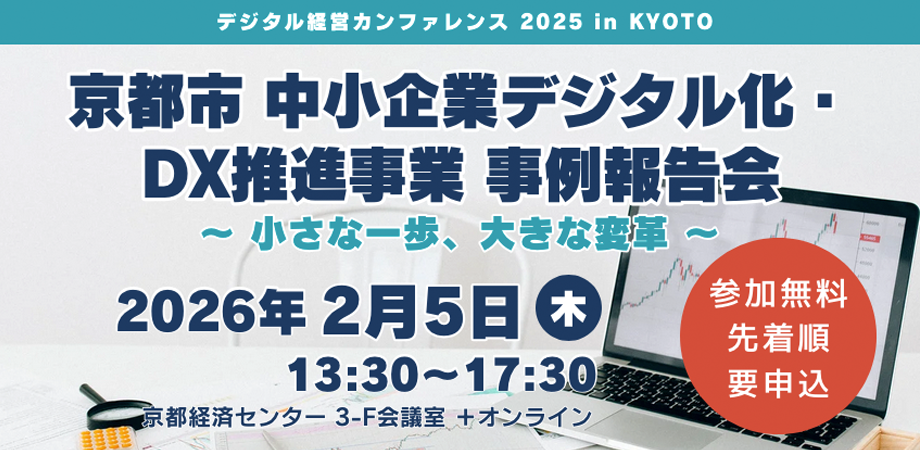1.現場で感じる「世代の壁」、それは課題か、それとも機会か?
「若い子はスマホばかり触っている」「ベテランに聞かないと分からないことが多すぎる」「デジタル化を進めたいが、年配の職人さんはついていけない」
このような声を、製造業の現場でよく耳にします。実際に多くの中小製造業では、長年現場を支えてきた50歳以上のベテラン従業員と、デジタル機器に慣れ親しんだ30歳未満の若手従業員の間に、深刻なコミュニケーションの溝が生まれています。
しかし、この「世代間ギャップ」を単なる問題として片付けてしまうのはもったいないことです。適切にマネジメントすることで、むしろ企業の競争力を大幅に向上させる強力な武器に変えることができるのです。
数字で見る製造業の現実 – 進む高齢化と若手不足
~想像以上に進んでいる現場の高齢化~
現場で起きている世代間の意識の違い
~全く異なる仕事への取り組み方~
情報共有方法の違いが生む非効率
ベテラン従業員は紙ベースの記録や直接的な口頭での情報伝達を好む一方、若手従業員はデジタルツールを使った効率的な情報共有を当然と考えています。
実際、製造現場で新たにデジタルツールを導入してデータを入力しても、管理者からは帳票にまとめた報告を求められるため、現場の職長などが残業してレポートをまとめる作業を行っていることなどは、今でもよくある話です。
2.DXが架け橋となる新しい可能性
「見える化」が生み出す共通理解
製造管理データの活用やペーパーレス化は中小製造業でのデジタル化の最初のステップであるといえます。加えてデジタル技術の最大の力は、これまで言葉で表現することが困難だった製造技術も「見える化」できることです。
例えば、金属の精密加工などいわゆる匠の技でつくられてきた製造プロセスが、センサー技術を活用することで、ベテラン職人の動きや設備の運転状況などを数値化して記録でき、製造ノウハウとして蓄積できます。
筆者自身も1980年代、造船会社における溶接ロボット開発をしていた際、品質良く仕上げることが難しい垂直方向の溶接をロボットで実現するために、名人と言われる溶接職人に何度も施工してもらいながら、その手の動きを真似てNCデータ化していく作業を延々と繰り返した記憶があります。当時は自分の目で見たものをデータ化するしかありませんでしたので、ロボットが上手に溶接できるようになるまでには、かなりの時間がかかりました。今ではカメラ映像やモーションセンサーなど様々なデバイスも使うことによって、素早く実現できるものと思われます。
データが支える技術継承の加速
このようにデジタルでプロセスをデータ化することで、ベテランが経験で培った感覚を、若手に継承することを支援することができます。
また、従来の技術継承は、主に師匠から弟子への1対1の指導に依存していましたが、デジタル技術を活用すると、一人のベテランの技術を複数の若手に同時に、しかも効率的に継承することが可能になります。
3.中小製造業における現実的なDX導入戦略
~段階的に進める。まずは小さく始める第一歩~
第1段階:現状の「見える化」
最初に取り組むべきは、現状の「見える化」です。製造現場で管理すべき作業時間、出来高などの正確な記録、品質データや測定器の計測値など、基本的なデータ収集から始めます。
製造工程内の様々なデータが蓄積されてくると、製造工程での設備稼働率や作業者の生産能率、生産進捗などが見える化できます。この段階では直接的に大きな変化は期待できませんが、客観的なデータが蓄積されることで、これまで感覚的に捉えていた課題が具体的に把握できるようになります。また、従業員全体の意識改革のきっかけとしても重要な役割を果たします。
第2段階:標準化と共有化を進める
データの蓄積がある程度進んだら、次は標準化と共有化に取り組みます。作業手順の動画マニュアル化やクラウド型の情報共有システムの導入により、技術継承の効率が大幅に向上します。
重要なのは、この段階でベテランと若手の両方が積極的に参加することです。ベテランには動画撮影や手順書作成に協力してもらい、若手にはデータ分析や システム運用を担当してもらうことで、お互いの強みを活かした協働体制を築くことができます。
これこそが、世代間ギャップを競争力に変えていくプロセスだと言えます。
第3段階:AIと自動化を実現
データ基盤が整ってくると、進化の著しいAI技術を活用して、従来よりも精度のよい品質判定や、予防保全などの仕組みを構築することができます。世代間ギャップを乗り越えて企業の持つ貴重な経験・技術資産をデジタル化し、それを活かす仕組みを構築することで、将来の成長につながる競争力の確立が期待できます。
世代間協働を促進する組織づくり
~異世代混合チームの効果~
成功している企業では、意図的に異なる世代を組み合わせたプロジェクトチームを編成しています。50歳以上のベテラン技術者と30歳未満の若手技術者をメンバーとして組み合わせることで、ベテランの経験知と若手のデジタルスキルが融合し、従来では考えられなかった革新的な改善案や技術開発が生まれることも多くあります。
世代間のコミュニケーションも活性化し、会社の一体感が増すことも期待されます。
4.まとめ
~世代間ギャップを成長の原動力に~
製造業における世代間ギャップは確かに大きな課題ですが、見方を変えれば、異なる強みを持つ人材が共存する貴重な「多様性」でもあります。50歳以上のベテランが持つ豊富な経験と洞察力、30歳未満の若手が持つデジタルスキルと柔軟な発想力を適切に組み合わせることで、これまでにない革新的な成果を生み出すことができます。
デジタル技術は、この異なる世代をつなぐ共通言語として機能します。ベテランの感覚的な技術をデータとして可視化し、若手のデジタルスキルを活用してそれを分析・改善する。このプロセスを継続することで、単なる技術継承を超えた、組織全体の知的資産の蓄積と活用が可能になります。
人手不足が深刻化する中、限られた人材で最大の成果を出すためには、世代を超えた協働が不可欠です。変化を恐れず、一歩ずつでもデジタル化・DXに取り組むことが世代間のギャップを企業の競争力に変える大きな力になるのです。
◆ 執筆者プロフィール
安尾 典之(やすお のりゆき)
ITコーディネータ京都 理事(教育企画)
DXビジネス検定エキスパート
造船、総合電機、産業機器などのメーカーでFA開発や工場責任者などを担当。
現在は建設土木系企業でDX推進を担当
e-mail:noriyuki.yasuo@gmail.com