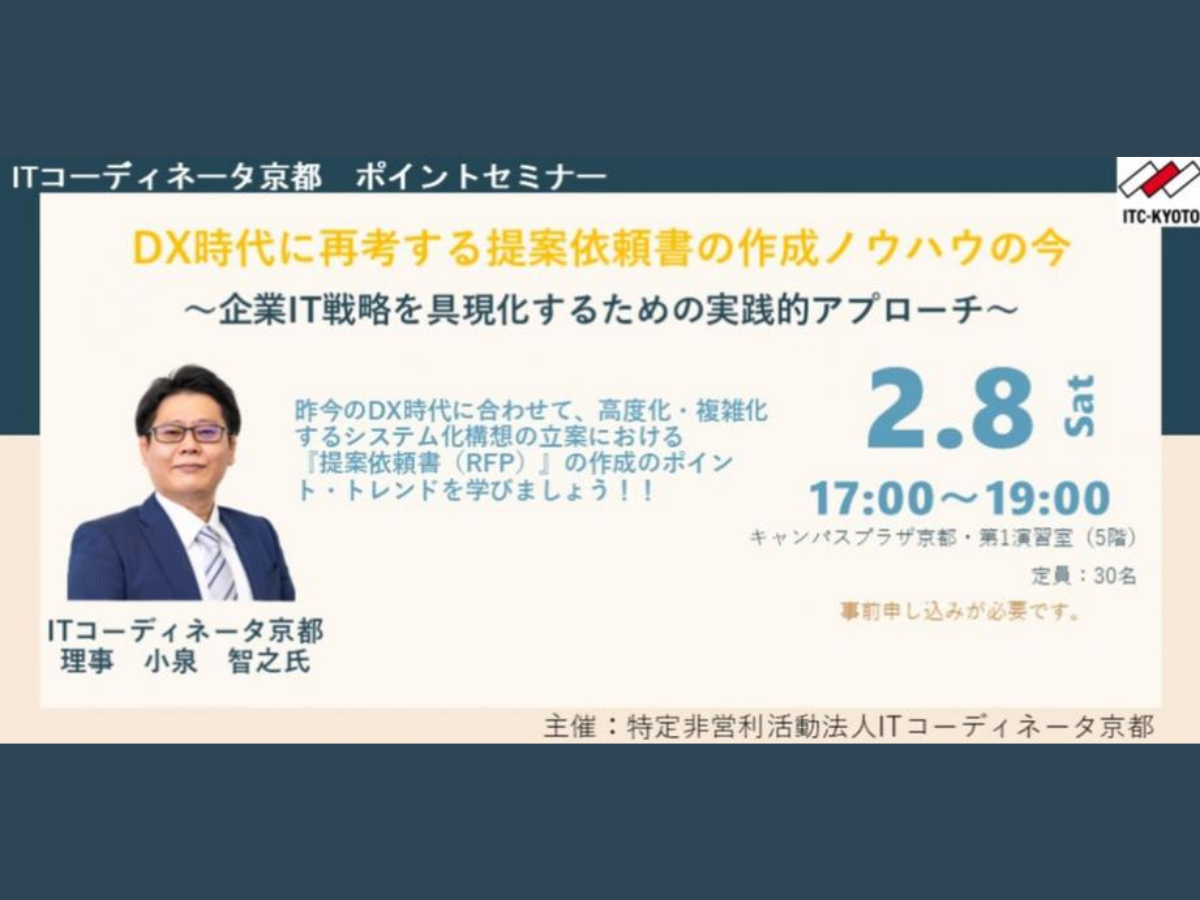今回は少しアカデミックな内容を書きます。企業の競争戦略についてのテーマです。
最近書かれた以下の論文が注目されています。
「生成AIで持続的な競争優位は築けない-独自のリソースとケイパビリティはあるか」
・要約
「各業界で早期に生成AIを使い始めた賢く機敏な一部企業は、 その価値を短期間のうちに享受してきたことは間違いない。 だが、 どの業界であれ、生き残った企業はすべて近いうちに生成AIを使い始めるだろう。そうなれば、 どの企業にとっても生成AIは競争優位の源泉ではなくなる。その段階で勝ち残るのは、すでに持っていた競争優位を生成AIで強化できた企業となるだろう。」
“AI won’t give you a new sustainable advantage. “Jey B. Berney, Martin Reeves, Diamond Harvard Business Review December 2024.
生成AIの機能は短期間で著しく向上し、企業での活用も進んでいます。それと並行して、ビジネス誌での生成AIに関する議論も活発になっています。
生成AIが人の創造性をどのように拡張するかという点から始まり、人の仕事の『補完』か『代替』か、法的・倫理的問題への対応など活用にあたっての課題認識へと進み、次のステップとして、生成AIの戦略的活用から生成AIネイティブ時代への対応へと論点が進んでいるように感じます。
こうして数年間を振り返ってみてもすごいスピードです。これが「生成AIネイティブ時代」への変化なのでしょうか。
今回のコラムは、生成AI時代に企業はいかに競争優位を構築していくかに着目して書きます。生成AIの新機能登場に一喜一憂している時代は過ぎ、地に足を付けた企業の持続的競争優位をいかにして構築していくかを検討していきます。
最初に断っておきますが、このコラムは生成AIの役割を否定するものではありません。生成AIの活用は慎重にと主張するものでもありません。私たちの社会・ビジネス環境は、すでに「生成AIの活用を前提」に進んでいるのですから。
先に紹介した論文の要点を私流にまとめると以下の通りです。
・生成AIを先進的に活用している企業は、一時的に競争優位を実現している。
・しかし、生成AIの進化は速く活用法の模倣も容易である。したがって、その優位は一時的なものにとどまる。生成AIの新機能へのキャッチアップは他の企業に任せ、成功した企業のやり方を模倣するのが近道である。
・生成AIの活用だけでは持続的な競争優位は築けない。自社の本来の強みに着目し、その強化に努めるべきである。
みなさんは、この論文の主張をどう思われますか?
持続的競争優位とは?
生成AIと企業の競争優位の話に入る前に、企業の競争戦略について少し整理をしておきます。事業の競争上の位置は一般的に(持続的)競争優位、競争同位、競争劣位の3つに区分されます。まとめると以下のようになります。
競争戦略における3つの立ち位置:持続的競争優位とは何か
(持続的)競争優位:他社には容易に模倣できない強みを持ち、長期間にわたり市場で優れた地位と高い収益を維持できる状態。差別化やコスト優位などが確立されており、競争圧力にも強い。 |
競争同位:競合他社とほぼ同等の競争力を持ち、特に優位でも劣位でもない中間的な位置。市場シェアや収益性も平均的であり、環境変化次第で上位にも下位にも動く可能性がある。 |
競争劣位:競合他社に比べて劣った競争力しか持たず、市場での地位や収益性が低い状態。価格競争に巻き込まれやすく、戦略の抜本的見直しや競争軸の転換が求められる。 |
注:ChatGPTで作成
持続的競争優位を実現している企業は、高い収益性を確保し長期にわたって業界上位の地位を維持しています。それに対して競争同位の企業は中間的な不安定な位置にあり環境変化の影響を受けやすくなります。
生成AIで持続的競争優位は築けない
本題の論点に入ります。
生成AIの登場は、従来の産業構造を大きく変えるインパクトがあるように思います。従来の産業の一部が衰退し、新しいタイプの産業が登場する可能性があります。
J. B. Barneyは、先の論文で「生成AIは常に広く普及し、誰もが容易にアクセスできる技術であるため、それ自体を競争優位の源泉とすることは難しい。」と述べています。
生成AIは、持続的競争優位を実現する要件である希少性(Rarity)と模倣困難性(Imitability)を満たしていないと述べています。つまり、どの企業も同じような生成AIツールを使用できるため、技術自体に独自性や持続性を持たせることが困難である。また、生成AIはデータやモデルの改善を通じて短期的なパフォーマンス向上には寄与するが、競合他社も同様に導入・適応できるため、長期的な差別化にはつながりにくい。
したがって、生成AIを活用して一時的な競争上の利益を得ることは可能でも、それを持続的な競争優位に結びつけるためには、企業固有の資源や組織能力(たとえば、独自のデータ活用能力や組織文化)と結びつける工夫が不可欠であるとバーニーは主張しています。
生成AIを使いこなすだけでは、競争同位は実現できても持続的競争優位は実現できない、との結論になります。競争相手と同じレベルを実現しているだけでは競争には勝てないのです。
いかにして持続的競争優位を実現するか!
J.B. Barneyは論文の中で、生成AIそのものでは持続的競争優位は築けないが、生成AIを「自社固有のリソースやケイパビリティ(組織能力)」と結びつければ可能性がある、と述べています。
具体的には、次のような要素が必要だと指摘しています。
生成AI活用を競争優位に変える企業固有の要件
独自のデータ資源(Proprietary Data):生成AIに使うデータが公開情報ではなく、自社しか持っていない特有のデータであること。これにより、他社が真似できないアウトプットやサービスを生み出せる。 |
組織固有の運用能力(Organizational Capabilities):生成AIをどのように業務プロセスに組み込み、活用するかについて、他社には模倣できないノウハウや運用体制を確立すること。 |
独自の学習・改善プロセス(Continuous Learning Systems):生成AIを導入した後、単なる利用にとどまらず、自社の経験を通じて運用方法やモデルを独自に進化させていくプロセスを持つこと。 |
注:論文を元に著者作成
やや抽象的な表現が多いですが、生成AIという「汎用的なツール」を、企業固有の資源・能力と結びつけて「唯一無二の強みに変えること」が必要だと述べています。
“インターネットの活用で競争優位を実現する??”
蛇足ながら、このバーニーの論文を読んでいて昔の論文を思い出しました。マイケル・ポーターが2001年に発表した「戦略の本質は変わらない:Strategy and the Internet」という論文です。
・要約
「『インターネット時代には戦略など無意味だ』という意見をよく聞く。しかし、事実はまったく逆である。インターネットの活用は、オペレーション上で独自の競争優位をもたらすことなしに、産業全体の収益性を弱める傾向を持つ。それゆえ、これまで以上に差別化を図る戦略が大切になっている。インターネットは従来の競争手法を補完するものであり、そのように振る舞う企業が勝利を手にすることになろう。」
マイケル E.ポーター 「戦略の本質は変わらない」Strategy and the Internet, Diamond Harvard Business Review May,2001
現在は、“インターネット・ネイティブ”の時代です。企業活動においては、インターネットを使うことが当たり前で不可欠な社会インフラとなっています。この論文が書かれた25年前には「インターネットの活用で競争優位を実現する」との主張が多く出ていたようです。隔世の感があります!
確かにインターネットは市場環境を変えました。衰退した企業も多い一方で、生き残って成長している企業は、もともとの強みを持っていた企業であったように感じます。
生成AIもインターネットのように不可欠な社会インフラとなっていくでしょう。進化のスピードからするとインターネットが社会に浸透するのに掛かった時間より早くなりそうです。私たちは、“生成AIネイティブ”時代の入り口にいます。
◆ 参考文献
・Jey B. Berney, Martin Reeves、「生成AIで持続的な競争優位は築けない-独自のリソースとケイパビリティはあるか:AI won’t give you a new sustainable advantage.」、ダイヤモンド社、Diamond Harvard Business Review 2024年12月.
・Jey B. Berney、訳:岡田正大、「企業戦略論(上)基本編 競争優位の構築と持続」、ダイヤモンド社、2003年.
・マイケル E.ポーター 「戦略の本質は変わらない:Strategy and the Internet」、ダイヤモンド社、 Diamond Harvard Business Review 2001年5月.
◆ 執筆者プロフィール
藤原正樹(フジワラ マサキ)
ITコーディネータ京都 副理事長
京都情報大学院大学 教授
宮城大学 客員教授
博士(経営情報学) 中小企業診断士 ITコーディネータ
e-mail:m_fujiwara@kcg.ac.jp
Web: https://www.fujiwaralab.jp/