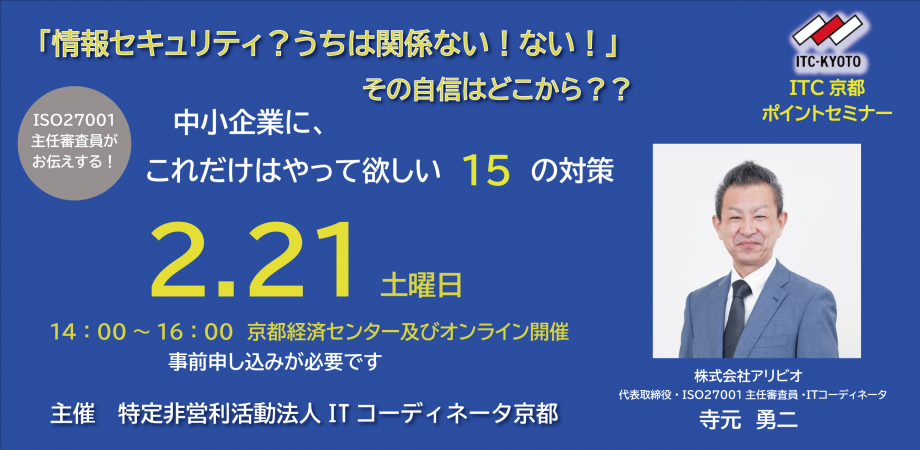はじめに:避けては通れない「生成AI」という大きな波
ITコーディネータとして日々企業の皆様と接する中で、『ChatGPT』に代表される生成AIの急速な進化とビジネスへのインパクトを肌で感じています。「一部の大手企業やIT企業だけの話でしょう?」と思われるかもしれませんが、その波はすでに、地域を支える中小企業にとっても、決して他人事ではいられない時が早々にやってくると想像できます。
しかし、これを脅威ととらえずに、むしろ、リソースの限られる中小企業にとって、大きなチャンスととらえて日々の企業運営や事業に活かしていきたいものです。
本コラムでは、ITコーディネータである私自身の仕事が、生成AIによって短期間でどう変化したか、そのリアルな現場をご紹介します。そして、その経験を通じて見えてきた「中小企業が明日からできる、生成AIの具体的な活用法」を簡単ないくつかの例でお伝えしたいと思います。
【本コラムをお読みいただく上での重要な注意点】
本文では生成AIのいくつかの活用法をご紹介しますが、安全にご利用いただくために、以下のルールを必ずお守りください。
• お客様の個人情報や企業固有情報、社外秘の機密情報は絶対に入力しないでください。
• 多くのサービスには、入力した情報をAIの学習から除外する「オプトアウト」設定があります。IT担当や外部専門家にも相談の上、ツールの利用前に必ず設定を確認しましょう。
【変化1】企業分析が「検索」から「生成AIによる統合リサーチ」へ深化
従来、訪問先の企業を調査するには、HP、IR情報、業界サイトなどを見て回り、情報を入手して簡単に整理しておくことを事前準備としてよくしていました。
現在、私の主な情報収集はGoogleのGeminiが持つリサーチ機能(いわゆるディープリサーチ)を活用しています。例えば、次のようなプロンプトで指示を出すのです。
【プロンプト例】
「京都市にある〇〇工業について、詳しく調査してください。
• 会社の基本情報
• 事業内容と主要製品・サービス
• これまでの沿革
• SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)
• 公開情報からわかる範囲での簡単な財務分析
上記の項目について、信頼できる情報源から情報をまとめてください。」
すると、わずか数分で質の高い調査レポートの骨子を手に入れることができます。この他にも、調査の際に情報源を明記してくれる信頼性の高いPerplexityのようなツールもあり、目的に応じて使い分けることも有効です。
もちろん最終的な事実確認は必須ですが、情報収集にかかる時間は圧倒的に短縮されました。
これにより、本質的な「思考」と「分析」に時間を注げるようになったのです。
―Geminiのディープリサーチで「ITコーディネータ京都」を調査した例―
【変化2】資料作成が「高速化」し、思考のための時間を生み出す
議事録や報告書の作成も劇的に変わりました。会議の音声はスマートフォンのアプリ(私の場合、スマホのGoogle Pixelのレコーダー機能)で録音と同時に文字起こしした後、会社のセキュリティポリシーで許可されたAIツールを使って要約します。「決定事項とToDoをまとめて」といった指示で、精度の高い議事メモが一瞬で完成します。
また、提案書作成では「Genspark」のようなプレゼン生成に強みを持つツールも活用します。ここでも、顧客の機密情報の利用は避け、匿名化・一般化した要点や公開情報に基づいた情報をINPUTとした上で、プレゼン資料の構成案や各スライドのドラフトを生成AIに作らせることで、資料作成の負担を低減できます。
(利用する際は、入力した情報がAIの学習に利用されない設定になっているか、あるいは組織内での利用に限定された法人向けサービスであることを必ず確認してください。)
【変化3】「第二の脳」とAIを繋ぎ、思考を深めるパートナーへ
コンサルタントの価値は、情報をどう結びつけ、独自の洞察やアイデアを生み出すかにかかっています。この「思考」のプロセスで、生成AIは自身の思考パートナーになります。
私は普段から、「Obsidian」というツールに、思考の元となる情報を集約しています。お客様との対話で感じ取ったよくある課題(※匿名化・抽象化します)はもちろん、デジタル化やDXに関する記事のWebクリップ、過去に生成AIでリサーチ(ディープリサーチ)した結果の要約、そして日々のひらめきなどです。これら全てがMarkdownという形式のテキストファイルとしてここに蓄積されていきます。
そして、この「第二の脳」に蓄積した一次情報こそが、生成AIとの対話で強力な武器になります。例えば、新しいセミナーを企画する際、まずObsidianの中から関連する過去のメモやアイデアをいくつか選び出し、その内容を生成AIにインプットした上で、思考の壁打ちを始めます。
※もう少し専門的な仕組みを使うと生成AIからこのObsidianのファイルの塊にプロンプトから
の指示で直接アクセスすることも可能で、とても便利です。
【プロンプト例】
「あなたは、中小企業のDX支援を専門とする経験豊富なセミナー講師です。
以下は、私がObsidianに書き溜めている『製造業向けのDX入門セミナー』に関するアイデアの断片です。
(ここにObsidianからコピーしたアイデアメモを貼り付ける)
上記の情報を元に、以下の壁打ちに付き合ってください。
1. これらのアイデアを元に、2時間のセミナーとして魅力的な構成案(アジェンダ)を作成してください。
2. 参加者が『明日から試そう』と思えるような、具体的なワークショップのアイデアを2つ提案してください。
3. このセミナーを企画する上で、私が見落としている可能性のある視点や、追加すべきトピックがあれば指摘してください。」
このように、自分自身のメモを元に生成AIと対話することで、生成AIは単なる情報検索ツールから、私の思考を客観的に整理し、新たな視点を与え、アイデアを飛躍させてくれる「思考パートナー」へと変わるのです。
上記のツールなどの活用事例以外にも、昨今話題であるGoogleが提供しているNotebookLMなども自身の知恵知見や情報源(Webサイト・公開情報)によるアイデア出しや企画検討などに使えます。
【変化4】WebサイトやUIの試作が「アイデア」から「可視化」へ
Webサイトのリニューアルや、簡単な社内システムの画面を検討する際、これまではPowerPointで画面の構成案を作ったり、Excelや画像ツールでワイヤーフレーム(設計図)を作成したりと、既存のツールで時間をかけてイメージを共有していました。ここに生成AIを活用することで、アイデアを即座に「目に見える形」にできるようになりました。
具体的には、「v0.dev」や「Bolt」のようなUI生成サービスを使います。例えば、次のようなプロンプトで指示を出すのです。
【プロンプト例】
「中小の製造業向けの、信頼感と先進性を感じさせるコーポレートサイトのトップページを作成してください。ヒーローセクションには製品画像とキャッチコピー、その下には『事業内容』『技術紹介』『会社概要』へのナビゲーションを配置してください。」
すると、ほんの数十秒でWebページの(たたき台)が生成されます。もちろん、これがそのまま完成品になるわけではありません。しかし、デザイナーや開発者と具体的なイメージを共有しながら議論を進めるための出発点としては、これ以上ないほど強力なツールです。アイデアを素早く形にすることで、手戻りが減り、プロジェクト全体のスピードアップに繋がっています。
ちなみに、私達のIT専門領域においては、プログラミング・ソフト開発の生成AIツールがどんどん新しいものがリリースされ、ソフトウェアの開発プロセスも様変わりしようとしています。
明日からできる!中小企業のための生成AI活用・はじめの一歩
ここまで読んで、「専門家だからできるのでは?」と思われたかもしれません。しかし、そんなことはありません。大切なのは、まず一歩を踏み出すことです。
Step 1: 完璧を目指さず、まず「対話」してみる
最初の一歩は、とにかく使ってみることです。もし何から始めればいいか分からなければ、それすら生成AIに聞いてみましょう。
【こんな質問から始めてみよう】
「私は中小企業の経理担当です。明日から生成AIを仕事で使ってみたいのですが、何から始めればいいか分かりません。誰でも簡単に試せる、具体的な使い方のアイデアを5つ教えてください。」
生成AIは、あなたの最も身近な相談相手にもなってくれます。
Step 2: 「トライ&エラー」の中から、自社の使い方を見つける
大切なのは、完璧な答えを求めることではなく、まず試してみる(トライする)ことです。メールの返信文を作ってもらったら少し楽ができた、調べものの時間が短くなった。そんな「小さな成功体験」を積み重ね、試行錯誤(トライ&エラー)の中から、ご自身の、そして自社に合った活用法を見つけ出していくことが何よりも重要です。
おわりに:未来を創るパートナーとして
生成AIは、私たちの仕事を奪う脅威ではありません。人間の能力を拡張し、創造性を高めてくれる強力なパートナーです。特に、人手不足といった課題を抱えながらも、日々創意工夫を重ねておられる中小企業の皆様にとって、頼りになる相棒になってくれるでしょう。
生成AIの進化は非常に速く、今日できなかったことが明日には可能になる、そんな時代です。まずは、トライしてみる。その小さな一歩が、重要です。
◆ 執筆者プロフィール
小泉 智之
ITコーディネータ京都理事
中小企業診断士、ITコーディネータ、ITストラテジスト、プロジェクトマネージャ